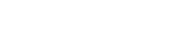内装工事に関する勘定科目は4つ!費用の会計処理に必要な知識
内装工事は頻繁に行われることが多いので、費用として計上するときの会計処理にお困りの方も多いのではないでしょうか。
仕訳をするには勘定科目が必要ですが、内装工事に関する勘定科目はそれほど多くありません。そのため、一度理解してしまえば、比較的やりやすいでしょう。
そこで今回は、内装工事に関する勘定科目や、仕訳をするために必要な基礎知識をお話しします。しっかりと理解して、経理業務に役立ててください。
内装工事の費用を仕訳する前の基礎知識
内装工事の会計処理は、勘定科目の仕訳をし、耐用年数を出して、減価償却の計算をするといった流れで行います。そのため、まずは耐用年数と減価償却についての基礎知識をお話しします。
減価償却とは
減価償却とは、機械や備品などを使用していくにつれて、もともとあった価値が時間とともに失われていくのを費用として計上するときに使う勘定科目です。減価償却を行う資産は、減価償却資産といいます。
減価償却資産は、一度に費用として計上することはしません。その資産の耐用年数によって、毎年分割して計上していきます。
なぜ分割して計上するのかというと、一度に大きな金額を費用として計上すると、実際の収益と経費の割合が合わなくなってしまうからです。高額な費用を計上すると、その年が赤字となってしまい、銀行からの融資を受けられなくなってしまうおそれがあります。
そのような事態を避けるべく、減価償却処理を行う必要があるのです。毎年一定額を費用として計上することで、実際の収益とバランスがとれます。
耐用年数とは
耐用年数とは、減価償却資産を使うことができる年数のことです。減価償却資産がどれくらいで価値がなくなるのかを表したもので、この耐用年数をもとに減価償却の計算をします。
耐用年数の決め方は明確なものこそありませんが、耐用年数によって毎年計上する経費が変わってきます。そのため、耐用年数は慎重に決める必要があるでしょう。
内装工事の勘定科目
内装工事の仕訳をする際に必要な勘定科目は、4つにわかれます。勘定科目は下記の内容です。
・建物
・建物付属設備
・経費
・備品
経費以外の勘定科目は、一度にまとめて計上するのではなく、減価償却処理をして、毎年分割して計上する必要があります。
耐用年数や減価償却の計算方法を間違えると、経費に差が生まれ、確定申告に影響がでます。そのため、仕訳に使う勘定科目の選定や減価償却の計算は、間違えないように注意しましょう。
建物
内装工事の勘定科目は、基本的に建物として仕訳します。しかし、新築であることが条件で、建築付属設備は含まれません。建物として仕訳するものがわからない場合は、建築付属設備を省いて、残りが建物だと判断するとよいでしょう。
建物として仕訳されるものは、以下のようなものがあります。
・防水工事
・ガラス工事
・木工工事
・造作工事
このような、建物に固定されている部分の工事に関しては、建物として仕訳しましょう。
建物付属設備
建物付属設備は、自動で機械が動かしてくれる設備のことをいい、建物に固定されている場合が多いです。備品との区別が付きにくいときは、下記の例を参考にしてください。
・ガス設備:ガスの元栓、配線、ガス機器の配置などが該当
・冷暖房設備:レストランやカフェなど、店舗に設置する冷暖房設備が該当。1台20万円以上であることが条件
・電気設備:電気を使用する際に使う照明の設置工事や、配線工事などが該当
・自動開閉設備:自動ドアのこと。自動ドアの設置工事は建築付属設備に該当
建物付属設備かどうか迷ったときは、自治体や国税庁の公式サイトに載っている耐用年数表を確認してみましょう。勘定科目が建物なのか建物付属設備なのかが、内容別にわかりやすく載っています。
万が一耐用年数表にも記載されていなかった場合は、税務署に問い合わせてみるか、担当の税理士に相談してみてください。ここからは、建物付属設備に分類されるものを具体的に説明していきます。
ガス設備
ガス設備は、美容室や飲食店などで使用するガス設備の内装工事を行った際に、必要な勘定科目です。
美容室では、シャンプー台でシャワーをする際にガスを使うため、ガス設備の内装工事が発生します。また飲食店では、給湯器やガスコンロなどガスを使う場所が多く、ガス設備の工事も頻繁に行われます。ガス栓の配置やガスの配管工事などが、この勘定科目にあたるでしょう。
電気設備
電気設備という勘定科目に分類されるものは、大きく分けて2種類あります。まずひとつ目が、蓄電池電源設備です。蓄電池電源設備は、災害時に照明などに利用できるよう蓄電池にあらかじめ電気を貯めておき、それを利用するための設備のことをいいます。
蓄電池には、リチウムイオン蓄電池、ニッケルカドミウムアルカリ蓄電池、鉛蓄電池などがあります。消防用設備として用いられているため、専門職以外の方には聞きなれない言葉でしょう。
そして2つ目は、蓄電池電源設備以外のものです。一般的な内装工事で、配線工事や照明器具の取り付けなどを行った場合は、こちらに該当します。そのため、大半が蓄電池電源設備以外のものになるでしょう。
冷暖房・ボイラー設備
冷暖房・ボイラー設備は、店舗内に設置されているエアコンのことです。しかし、すべてのエアコンが建物付属設備にあたるわけではありません。
建物付属設備にあたるのは、天井に埋め込まれているタイプで、かつ広い範囲の温度調整が可能なエアコンです。一般的な家庭にある設置型のエアコンは該当しないので注意しましょう。設置型のエアコンは、機器および備品として仕訳するので覚えておいてください。
昇降機設備
昇降機設備とは、人やものを建物内で別階に運ぶことのできる設備のことです。エスカレーターやエレベーターが該当します。
エレベーターの用途は、乗用・荷物用・病院患者用などさまざまあります。乗用の中にも、防災用の非常時専用エレベーターなどが存在します。
内装工事でエレベーターを設置する機会は多くないですが、飲食店で料理を運ぶための小型エレベーターを付けたり、介護施設で患者用エレベーターを追加したりといった事例があるでしょう。このような内装工事を行った場合は、昇降機設備の勘定科目を使用してください。
店用簡易装備
店用簡易装備とは、壁板・カウンター・陳列棚など建物として分類されない、簡易的な装飾のことをいいます。
陳列棚は、備品や器具に分類されないものが該当し、カウンターは床の上に置いてあるものではなく、取替え可能なもののみ該当します。店用簡易装備は細かく決まりがあるので、国税庁の公式サイトで確認するとよいでしょう。
基本的には、短期間で取り替えられることが予想されるものをさします。店用簡易装備は耐用年数3年と決められているため、その間に取り替える可能性のあるものが該当すると考えてください。
パーテーション
近年利用が増えているパーテーションは、建物に分類されるものと、建物付属設備に分類されるものがあります。どちらに分類されるのか判断する方法は、再生可能なものかどうかです。
再生不可能なものは、建物にあたります。たとえば、スライド式のドアのような形状をしたパーテーションは建物に固定されているため、勘定科目は建物です。
いっぽう再生可能なものは、建物付属設備にあたります。スタンドタイプのパーテーションや、上から吊るすタイプのパーテーションは建物付属設備です。持ち運びができるタイプかどうかで判断するとよいでしょう。
諸経費
工事の際、間接的に発生する経費を諸経費といいます。工事に必要な手続きで発生した手数料や、人件費などが諸経費にあたります。
人件費は明確に金額を出せますが、手数料など細かいものは内装工事の内訳を確認しなければ把握できません。内訳書に詳細が書いていない場合は、そのまま仕訳をすると間違えてしまう可能性が高いので、担当業者に確認しましょう。
備品
備品として分類されるのは、業務を行うために必要な消耗品です。たとえば、パソコン・電話・机・いすなどがあります。
壁や床に設置できて、なおかつ20万円以上でないと備品にはなりません。前述した、床の上においてあるタイプのカウンターは、備品に分類されることになります。
10万円~20万円以内のものは一括償却資産に、そして10万円以下のものは消耗品にあたります。消耗品の場合は減価償却の計算が必要なくなるので、覚えておきましょう。
まとめ
内装工事に関する勘定科目は、建物・建物付属設備・経費・備品の4つのみであることがわかりました。建物付属設備に関しては、分類が多くあるためわかりにくいかもしれませんが、一度覚えてしまえばややこしいものではありません。
勘定科目を間違えると、確定申告の際に間違った報告をすることになってしまうため、勘定科目はしっかり覚えるようにしましょう。
また、減価償却の計算も重要な部分です。減価償却を間違えてしまうと、費用として計上する金額が変わってくるため、あとあと仕訳を修正しなくてはいけなくなります。決算前に手間が増えてしまうので、間違えないように注意してください。